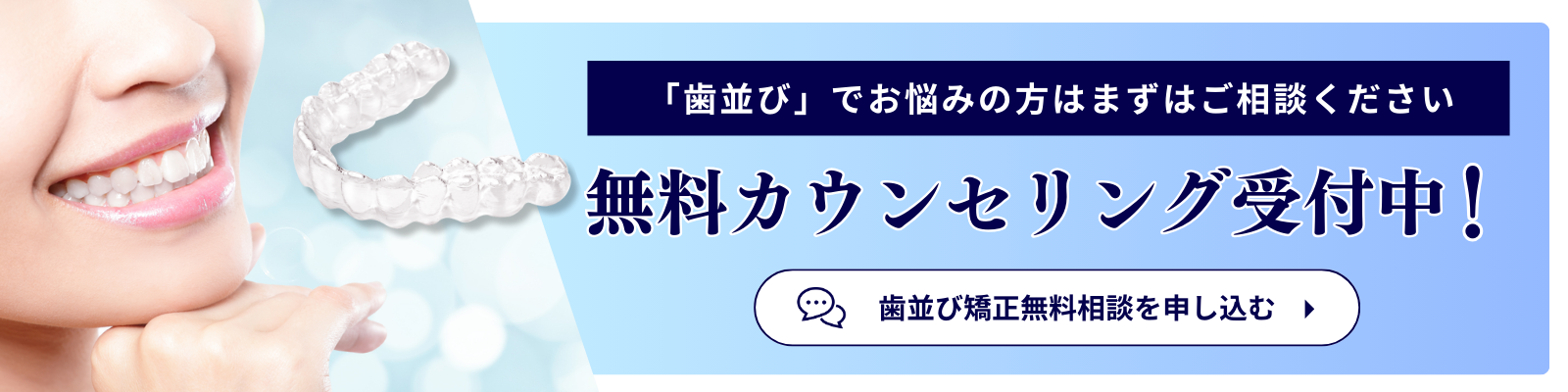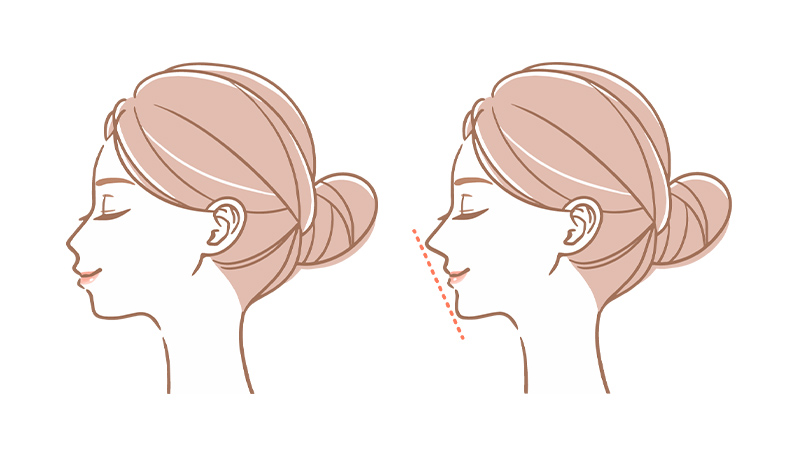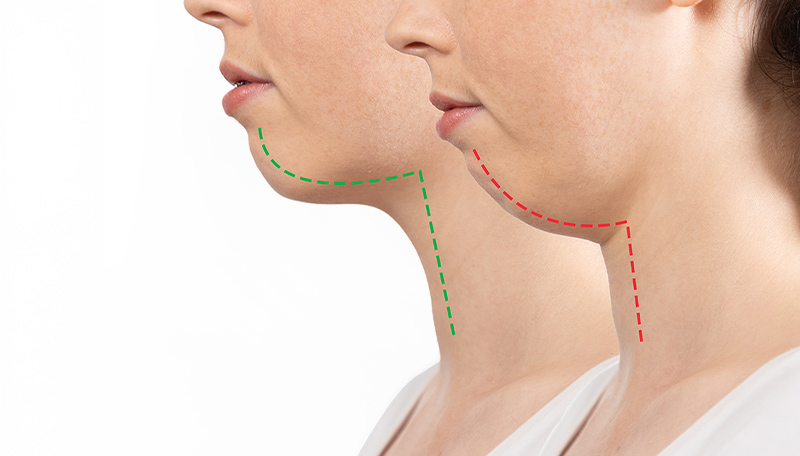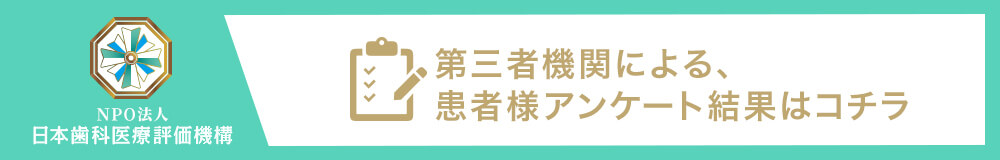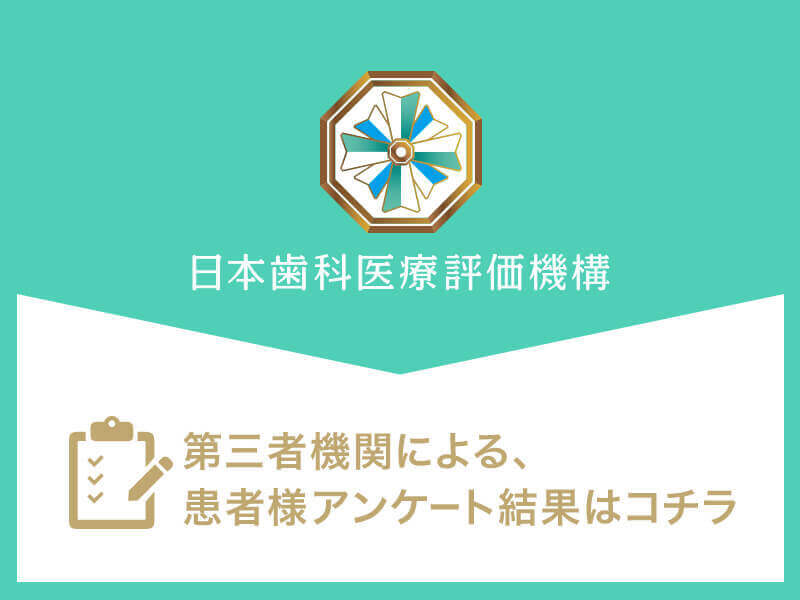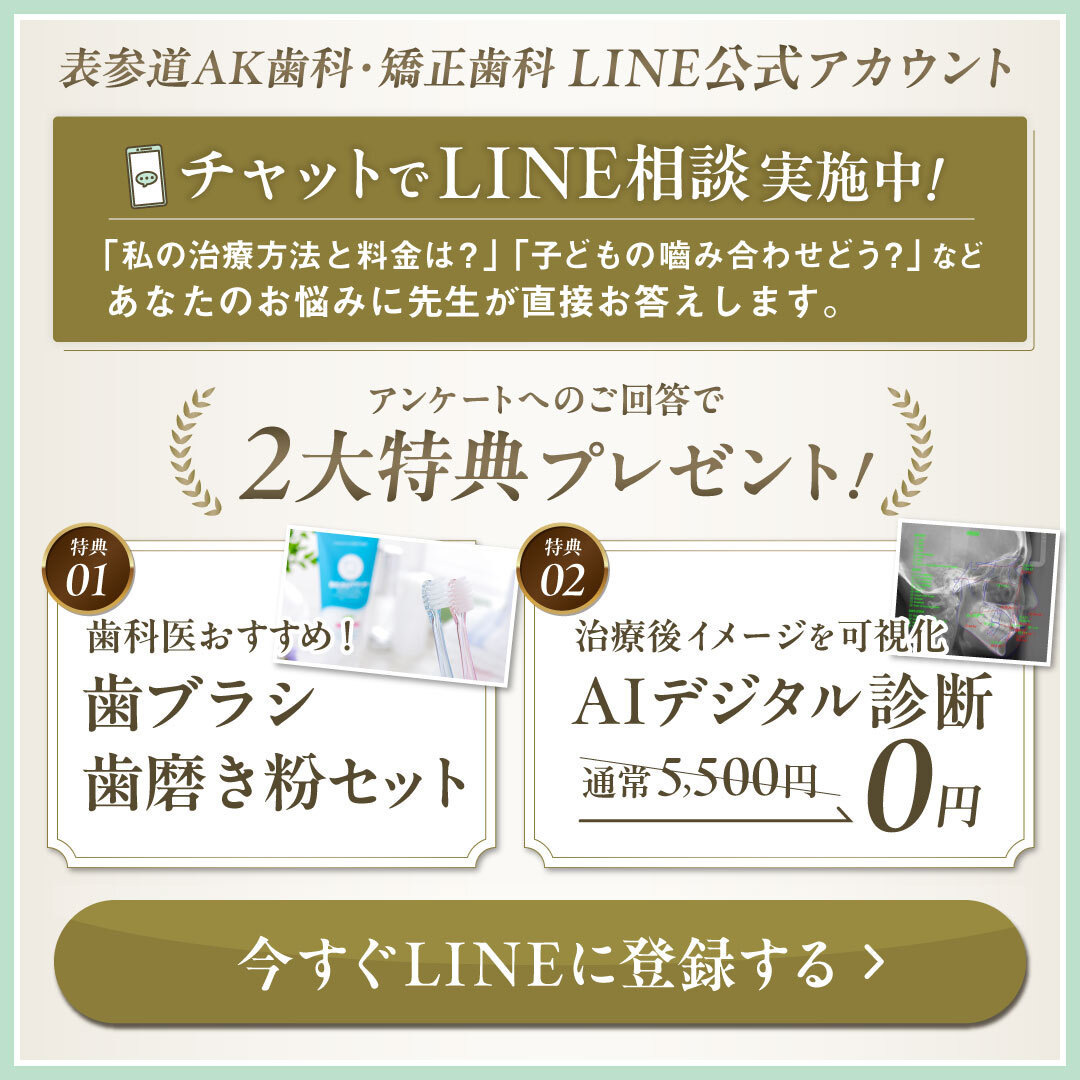
Contents
歯周病とは?進行のメカニズムを理解する

歯周病は、歯を支える組織に炎症が起こる病気です。初期の歯肉炎から始まり、放置すると歯周炎へと進行します。日本人成人の約8割が罹患しているとも言われ、歯を失う最大の原因となっています。
歯周病の主な原因は、歯の表面に付着する「プラーク(歯垢)」です。このプラークは細菌の塊で、「バイオフィルム」と呼ばれる被膜に覆われています。このバイオフィルムが細菌のバリアとなり、単なる水やうがいでは除去できないのが厄介なところなのです。
放置すると、プラーク内の細菌が歯肉に炎症を引き起こし、やがて歯を支える骨まで溶かしていきます。歯と歯肉の間にできる「歯周ポケット」が深くなるほど、歯を支える骨が失われていきます。最終的には歯がグラグラになり、抜歯に至ることもあるのです。
歯周病は単に口の中だけの問題ではありません。近年の研究では、歯周病と全身疾患との関連性も明らかになっています。特に糖尿病との関係は双方向的で、歯周病があると血糖コントロールが難しくなり、逆に糖尿病があると歯周病が悪化しやすくなるのです。
では、このような恐ろしい歯周病の進行を防ぐには、どうすればよいのでしょうか?
歯周病予防の基本:正しいブラッシング法
歯周病予防の第一歩は、正しいブラッシングです。多くの方が毎日歯磨きをしているにもかかわらず、歯周病になってしまうのはなぜでしょうか?それは、効果的なプラーク除去ができていないからです。
一般的な歯磨きに関する誤解をいくつか解消しましょう。まず、虫歯や歯周病の原因は食べ物そのものではなく、プラーク(細菌)です。また、歯磨き粉だけでは細菌は溶けません。バイオフィルムで覆われたプラークは、物理的な清掃が必要なのです。そして、歯ぐきは磨く必要がありません。プラークは歯の表面にしか付着しないため、歯ぐきを強く磨くと逆に傷つけてしまいます。
効果的なブラッシングのポイントは以下の通りです:
- 歯と歯肉の境目(歯頸部)を意識して磨く
- 歯ブラシは鉛筆持ちで軽く握り、強い力をかけない
- 小刻みに動かし、一カ所につき20回程度のブラッシングを行う
- 歯間ブラシやフロスで歯ブラシの届かない部分も清掃する
特に歯間部分の清掃は重要です。歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを完全に取り除くことはできません。歯間ブラシやフロスを併用することで、歯周病予防の効果が格段に上がります。
あなたは自分の歯磨きが正しいか、不安に感じることはありませんか?
実は、多くの方が「きちんと磨いている」と思っていても、実際には磨き残しがあるものです。歯科医院での定期検診時に、プロフェッショナルによるブラッシング指導を受けることをお勧めします。
プロフェッショナルケアの重要性
自宅でのセルフケアだけでは、歯周病を完全に予防することは難しいのが現実です。なぜなら、歯石となったプラークは歯ブラシでは除去できないからです。
歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアが、歯周病予防には欠かせません。具体的には、以下のようなケアが行われます。
- スケーリング:歯石や歯垢の除去
- ルートプレーニング:歯根面の清掃と平滑化
- PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning):専用器具による歯面清掃
- 歯周ポケット検査:歯周病の進行度チェック
特に歯周ポケットの検査は重要です。歯周ポケットとは、歯と歯肉の間にできる溝のことで、健康な状態では1〜3mm程度です。4mm以上になると歯周病が進行している可能性が高くなります。
歯周ポケットが深くなると、自分での清掃が届かない部分が増え、さらに歯周病が悪化するという悪循環に陥ります。定期的な検査で早期発見し、適切な処置を受けることが重要なのです。
では、どのくらいの頻度で歯科医院に通えばよいのでしょうか?
一般的には3〜4ヶ月に1回の定期検診がおすすめです。歯周病のリスクが高い方(喫煙者、糖尿病患者など)は、より頻繁な検診が必要になることもあります。
定期検診は「痛みがないから行かない」という方も多いですが、歯周病は初期には自覚症状がほとんどありません。痛みや出血が出始めた時には、すでにかなり進行していることが多いのです。
食生活の見直しで歯周病予防
食生活も歯周病予防に大きく関わっています。バランスの良い食事は免疫力を高め、歯周病に対する抵抗力を強化します。特に以下の栄養素は歯周組織の健康維持に重要です。
- ビタミンC:コラーゲン生成を促進し、歯肉の健康を維持
- カルシウム:歯や骨の形成に必要
- ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける
- タンパク質:組織の修復に必要
- 抗酸化物質:炎症を抑制
また、咀嚼(そしゃく)をしっかり行うことも重要です。よく噛むことで唾液の分泌が促進され、口腔内の自浄作用が高まります。唾液には抗菌作用もあり、歯周病菌の増殖を抑える効果があるのです。
反対に、糖分の多い食品や精製炭水化物の過剰摂取は、口腔内の酸性度を高め、歯周病菌の増殖を促進します。また、粘着性の高い食品は歯に付着しやすく、プラークの形成を助長します。
私の臨床経験では、食生活を見直すだけで歯肉の状態が劇的に改善した患者さんも少なくありません。特に糖分の摂取を減らし、野菜や魚を中心とした和食に切り替えた方は、数ヶ月で歯肉の炎症が落ち着くケースが多いです。
あなたも今日から、歯周病予防を意識した食生活を始めてみませんか?
禁煙は歯周病予防の強い味方
喫煙は歯周病の最大のリスク因子の一つです。タバコに含まれるニコチンやタールは、歯肉の血流を悪化させ、免疫機能を低下させます。その結果、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、歯周病が進行しやすくなるのです。
喫煙者は非喫煙者に比べて、歯周病になるリスクが2〜7倍も高いという研究結果もあります。また、喫煙者は歯周病治療の効果も出にくく、治療後の再発率も高いことが分かっています。
ある50代の患者さんは、20年以上の喫煙歴があり、重度の歯周病に悩まされていました。どんなに丁寧に歯を磨いても、歯肉からの出血や口臭が改善せず、歯もグラグラしてきていたのです。
禁煙を決意し、徐々に口腔内の状態が改善していきました。半年後には歯肉の色も健康的なピンク色に戻り、出血もほとんど見られなくなったのです。
禁煙は簡単ではありませんが、歯周病予防・改善のためには非常に効果的な方法です。禁煙外来や禁煙補助薬なども活用しながら、ぜひ禁煙にチャレンジしてみてください。
喫煙者の方、あなたの歯肉は今どんな状態ですか?
ストレス管理も歯周病予防に重要

意外に思われるかもしれませんが、ストレスも歯周病に大きく関わっています。過度のストレスは免疫機能を低下させ、体の炎症反応を促進します。その結果、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、歯周病が進行しやすくなるのです。
また、ストレスを感じると唾液の分泌量が減少することも問題です。唾液には口腔内を清潔に保つ自浄作用があるため、唾液が減ると歯周病菌が増殖しやすくなります。
さらに、ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりの習慣がある方も多いです。これらの習慣は歯周組織に過剰な負担をかけ、歯周病の進行を早める可能性があります。
30代の女性患者さんは、仕事のストレスが原因で重度の歯ぎしりがあり、歯周病が急速に進行していました。ナイトガードの使用と並行して、ストレス管理の方法を見直したところ、歯周組織の状態が徐々に改善していきました。
効果的なストレス管理の方法としては、以下のようなものがあります:
- 適度な運動
- 十分な睡眠
- 瞑想やヨガ
- 趣味や好きなことに時間を使う
- 深呼吸や呼吸法
歯ぎしりや食いしばりがある方は、歯科医院でナイトガード(マウスピース)を作製することも検討してください。これにより、歯周組織への過剰な負担を軽減することができます。
あなたは最近、ストレスを感じていませんか?もしそうなら、それが歯周病のリスクを高めているかもしれません。
最新の歯周病予防テクノロジー
歯周病予防の分野では、近年さまざまな新しいテクノロジーが登場しています。これらを活用することで、より効果的に歯周病を予防・管理することができるようになりました。
特に注目されているのが、「ブルーラジカル」と呼ばれる世界初の歯周病治療器です。これは青色レーザー(波長405nm)と過酸化水素(3%溶液)を利用して「ヒドロキシルラジカル」を生成する技術です。このラジカルは非常に高い酸化力を持ち、歯周ポケット内の細菌に対して強力な殺菌作用を発揮します。
従来の治療法では到達が難しかった歯周ポケットの深部の細菌にも効果的に作用し、しかも周囲の健康な組織にダメージを与えにくいという特徴があります。
また、患者さんの行動変容を促すアプリも開発されています。例えば「ペリミル」というウェブアプリでは、患者さんが自分の口腔内の状況を直感的に把握でき、歯磨きタイマーやスタンプ機能を使って習慣改善を促進します。さらに、歯科衛生士が治療後12週間のフォローを行える機能も搭載されています。
デジタル技術の進化により、3DスキャナーやAI分析を用いた正確な診断も可能になってきました。これにより、歯周病の早期発見や、より精密な治療計画の立案が可能になっています。
こうした最新テクノロジーは、すべての歯科医院で利用できるわけではありませんが、歯周病予防に力を入れている医院では積極的に導入されています。定期検診の際に、こうした新しい技術についても相談してみるとよいでしょう。
歯周病と全身疾患の関係を知る
歯周病は口の中だけの問題ではありません。近年の研究では、歯周病と全身疾患との深い関連性が明らかになっています。特に糖尿病との関係は双方向的で、お互いに悪影響を及ぼし合うことが分かっています。
歯周病があると、歯周ポケットから炎症性物質が血流に乗って全身に運ばれます。中等度以上の歯周ポケットが口の中全体にある場合、そのポケット表面積の合計は手のひらと同じ程度になると言われています。これは、手のひらサイズの炎症が体内にあるのと同じ状態なのです。
この炎症性物質がインスリンの働きを妨げ、血糖コントロールを難しくします。逆に、血糖値が高い状態が続くと、歯周組織の修復能力が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。
実際、歯周病の治療をきちんと行うと血糖値が改善するという研究結果も報告されています。
また、歯周病は糖尿病以外にも、以下のような全身疾患との関連が指摘されています:
- 心臓病・動脈硬化
- 脳卒中
- 肺炎
- 早産・低体重児出産
- 関節リウマチ
60代の男性患者さんは、長年コントロール不良の糖尿病と重度の歯周病に悩まされていました。歯周病の集中治療を行ったところ、3ヶ月後にはHbA1c(血糖値の指標)が1.2%も改善したのです。
このように、歯周病の予防・治療は口腔内の健康だけでなく、全身の健康維持にも大きく貢献します。特に糖尿病や心臓病などの持病がある方は、歯周病予防に特に注意を払う必要があるでしょう。
まとめ:歯周病予防で健康な歯を守ろう
歯周病は成人の歯を失う最大の原因ですが、適切な予防法を実践することで進行を防ぐことができます。この記事でご紹介した7つの方法をまとめると:
- 正しいブラッシング法:歯と歯肉の境目を意識し、歯間ブラシやフロスも併用する
- 定期的なプロフェッショナルケア:3〜4ヶ月に1回の歯科検診を受ける
- バランスの良い食生活:ビタミンCやカルシウムなど、歯周組織に必要な栄養素を摂取する
- 禁煙:喫煙は歯周病のリスクを大幅に高める
- ストレス管理:過度のストレスは免疫機能を低下させ、歯周病を悪化させる
- 最新テクノロジーの活用:ブルーラジカルなどの新技術を利用する
- 全身疾患との関連を理解する:特に糖尿病など持病がある方は歯周病予防に注力する
歯周病予防は一朝一夕にできるものではありません。日々の地道なケアの積み重ねが、将来の健康な歯を守ることにつながります。
私たち歯科医師・歯科衛生士は、患者様一人ひとりの口腔内の状態に合わせた最適な予防プログラムをご提案しています。「歯肉からの出血がある」「口臭が気になる」「歯がグラグラする感じがある」など、少しでも気になる症状があれば、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。
表参道AK歯科・矯正歯科では、歯周病の予防から治療まで幅広く対応しています。最新のデジタル機器を用いた精密な診断と、経験豊富な歯科医師による丁寧な治療で、あなたの大切な歯を守るお手伝いをいたします。
健康な歯で美味しく食事を楽しみ、自信を持って笑顔になれる毎日を過ごしましょう。
詳しい情報や無料カウンセリングについては、表参道AK歯科・矯正歯科までお気軽にお問い合わせください。
表参道AK歯科・矯正歯科 院長:小室 敦

https://doctorsfile.jp/h/197421/df/1/
略歴
- 日本歯科大学 卒業
- 日本歯科大学附属病院 研修医
- 都内歯科医院 勤務医
- 都内インプラントセンター 副院長
- 都内矯正歯科専門医院 勤務医
- 都内審美・矯正歯科専門医院 院長
所属団体
- 日本矯正歯科学会
- 日本口腔インプラント学会
- 日本歯周病学会
- 日本歯科審美学会
- 日本臨床歯科学会(東京SJCD)
- 包括的矯正歯科研究会
- 下間矯正研修会インストラクター
- レベルアンカレッジシステム(LAS)
参加講習会
- 口腔インプラント専修医認定100時間コース
- JIADS(ペリオコース)
- 下間矯正研修会レギュラーコース
- 下間矯正研修会アドバンスコース
- 石井歯内療法研修会
- SJCDレギュラーコース
- SJCDマスターコース
- SJCDマイクロコース
- コンセプトに基づく包括的矯正治療実践ベーシックコース (綿引 淳一 先生)
- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 診断・治療編(石川 晴夫 先生)
- 新臨床歯科矯正学研修会専門医コース 応用編(石川 晴夫 先生)
- レベルアンカレッジシステム(LAS)レギュラーコース
- 他多数参加